※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。
【ショートインターバルの実践方法】得られる効果・ペースとレストの設定方法を徹底解説
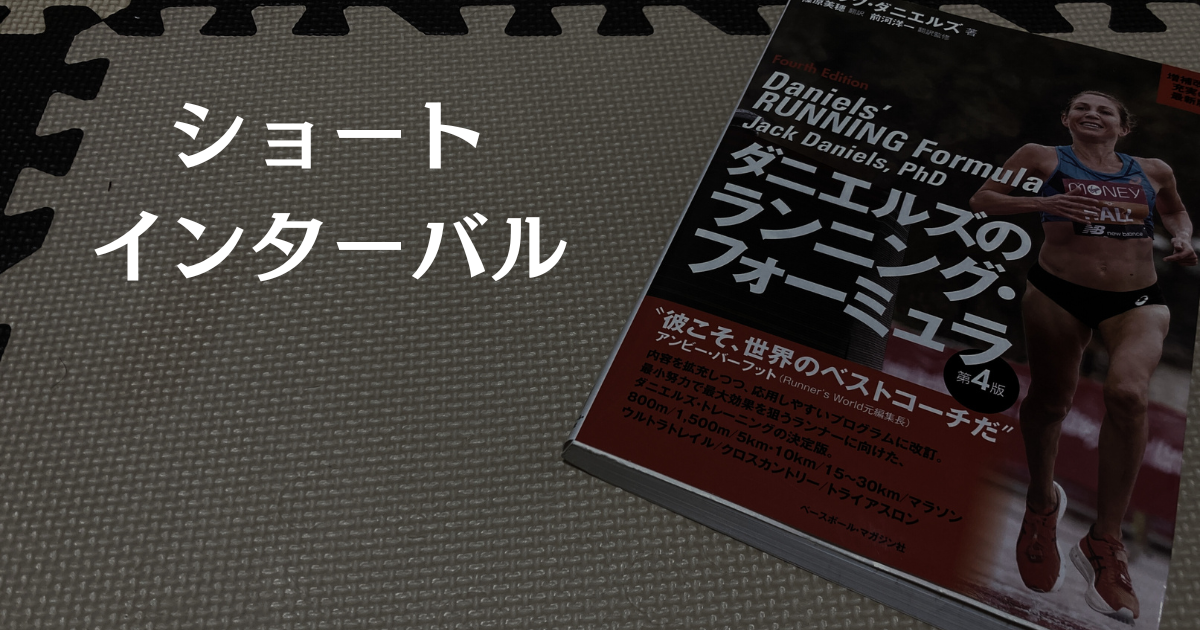
- ショートインターバルってなに?
- ショートインターバルの効果が知りたい
- 400mインターバルの具体的な設定タイムの決め方が知りたい
私は社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程を走り競技志向でランニングに取り組んでいます。
本記事ではインターバルトレーニングのバリエーションとして知られているショートインターバルについて、その効果を生理学的に考察し紹介します。
良く知られている代表的なインターバルトレーニングとしては、「1000m×5」などが挙げられます。しかし、インターバルトレーニングはペースとレスト、本数の設定により得られる効果が大きく変化します。
ペースやレストの設定方法によるショートインターバルで得られる効果、具体的なメニュー例を紹介します。
特に、VO2maxの向上を狙ったインターバルトレーニングの効果や実施方法については、次の記事で解説していますので参考にしてください。
本記事を読めば、ショートインターバルトレーニングを行うことによって得られる効果を理解することができ、適切なペース設定・レストの設定ができるようになります。
- ショートインターバルとは短めの疾走距離とレストを組み合わせて行うインターバルトレーニング
- ショートインターバルの効果として速筋繊維への刺激と解糖系代謝能力向上が見込める
- 「練習場所を確保しやすい・練習を失敗せずやり切りやすい」というメリットがある
- 200~600mの疾走距離と疾走時間の50~90%程度のレスト時間
ショートインターバルとは?
ショートインターバルとは、短めの疾走距離とレストを組み合わせて行うインターバルトレーニングです。
具体的な距離で言うと、200~600m程度の疾走距離と、30~60秒程度のレスト時間を組み合わせものになります。
ショートインターバルのメニューに似ているトレーニングとしてレペティショントレーニングがあります。ショートインターバルとレペティションは、レストの設定方法が大きく異なります。
ショートインターバルでは、疾走時間に対して50~90%程度のレスト時間で設定しますが、レペティションでは疾走時間に対して200~300%程度で設定します。
ショートインターバルに対して、1000m以上の疾走距離を設定するインターバルトレーニングをロングインターバルトレーニングと言います。
ショートインターバルで得られる効果
ショートインターバルで得られる効果は、ペース・レスト・本数の設定によって異なります。
ショートインターバルで得られる効果は以下の通りです。
- 速筋繊維への刺激、持久力の獲得
- 目標レースペースに対しての特異性向上
- 解糖系代謝能力の向上
- 乳酸性作業閾値の改善
- 最大酸素摂取量の向上
速筋繊維への刺激、持久力の獲得
ショートインターバルは短い疾走距離を繰り返すため、走行中に乳酸が溜まりにくいことが特徴です。疾走ペースを自分の5000m、速くても3000mのレースペース程度に抑えれば、ある程度の本数をこなすことができます。
例えば、疾走ペースを5000mレースペースに設定した場合、1000mに分割するよりも400mで分割したほうが体感的にも楽で、結果的に多くの本数をこなすことが可能です。
速いスピードで走るためにはより強い力を発揮する必要があるため、速筋繊維が多く動員されることになります。
筋繊維は使われることによって適応が進んでいきます。速筋繊維が何度も使われると速筋繊維の持久力が向上します。これは、中間型速筋繊維への変異と呼ばれます。
速筋繊維が持久力を獲得すると、速いスピードを長く維持することが可能になります。これを指標で表したものが「乳酸性作業閾値」であったり、「最大酸素摂取量」であったりします。
速筋繊維が持久力を獲得することについては、次の記事で詳しく解説しています。
目標レースペースに対しての特異性向上
これは主に、10000m以下のトラックレースを目標にしているランナーにとっての効果になります。
ショートインターバルは少しペースが速くても乳酸が溜まりにくいため「目標レースの疾走ペースでこなしやすい」という点があげられます。
5000mレースペースでの1000mインターバル(例えば1000mを5本)はそれなりにきつく、個人練習でコンスタントにこなしていくのは実際のところ、結構難しいです。
一方で400mに分割して、400mを12~15本、のようにすると比較的こなしやすいトレーニングになります。
目標レースペースに対して特異性を高めていくようなトレーニングとして、ショートインターバルは失敗が少ないトレーニングだと言えそうです。
ただ、例えば、1000m×5と400m×12を比較して、どちらの方が5000mレースに近いか?と言われれば、1000m×5の方が近い状況を作り出すことが可能です。
その意味で、疾走ペースが維持できるのであれば、1000m×5の方が特異性が高いトレーニングになります。
個人で練習するのか、集団で走れるのか、などによってトレーニングの内容はアレンジしていくことが望ましいです。
解糖系代謝能力の向上
ショートインターバルでは速筋繊維の動員が優位となるため、主なエネルギー原料は糖質であり、解糖系機能の向上がえられます。
糖質の代謝経路・解糖系についての説明は、次の記事を参考にしてください。
乳酸性作業閾値の改善
解糖系の中で乳酸が発生するため、発生した乳酸を代謝する能力も鍛えられます。
乳酸の代謝速度を決める要因の一つに、速筋繊維から血中に乳酸を拡散させるMCT4の働き(=乳酸放出能力)があります。
MCT4の増加や活性化は、速筋繊維を刺激するような高強度トレーニングでのみ認められることが分かっています。
最大酸素摂取量の向上
ショートインターバルトレーニングを行うことで最大酸素摂取量(VO2max)の向上が見込めます。
ただし最大酸素摂取量の向上を主目的にする場合はロングインターバルの方が適しています。VO2maxインターバルトレーニングについては、次の記事で解説しています。
ショートインターバルとロングインターバルの比較
ショートインターバルとロングインターバルで得られる効果を比較します。
| 項目 | ショートインターバル | ロングインターバル |
|---|---|---|
| 最大酸素摂取量 | 〇 | |
| 速筋繊維への刺激 | 〇 | |
| 解糖系への刺激 | 〇 | |
| 種目への特異性 | 〇 |
最大酸素摂取量向上:ロングインターバル
ダニエルズ理論では、最大酸素摂取量の状態となるためには、高強度の運動(90~95%VO2max以上)をし始めてから2分後であると述べられています。
また、疾走をくりかえすことによって最大酸素摂取状態となるまでの時間が短くなります。
ダニエルズ理論ではショートインターバルで最大酸素摂取量の向上効果を得るためには、レストを極力短くして疾走を繰り返すことが推奨されています。
ショートインターバルにも最大酸素摂取量の向上効果はありますが、最大酸素摂取量状態になる前、もしくは直後に疾走が終わるため、最大酸素摂取量への刺激量は結果的に少なくなります。
最大酸素摂取量への刺激はロングインターバルのほうが有利だと言えそうです。
ただし、ショートインターバルであっても繰り返し本数を多くすることで、トータルで得られる効果は高まります。
速筋繊維への刺激:ショートインターバル
ショートインターバルは、ロングインターバルと比較して「疾走速度(=VDOT%)を上げることができる点」が優位点です。
疾走速度を上げることで、運動強度が上昇し「速筋繊維」への刺激が多く入ります。
乳酸代謝を決める一要因として、速筋からの乳酸放出があり、速筋への刺激で機能が向上するため、この点はショートインターバルのほうが有利だと言えます。
また、速筋繊維を動員する強度でトレーニングを行うことで、速筋繊維が中間型速筋繊維(=FOG繊維)へ変化することを促します。
中間型速筋繊維は、速筋繊維と同じ力を発揮できることに加え、ミトコンドリアを多く含むため、糖質や脂肪を完全酸化しエネルギーに変える力に長けています。
解糖系への刺激:ショートインターバル
ロングインターバルよりもショートインターバルのほうが疾走速度を上げやすいことから、解糖系への刺激も強くなります。
最大酸素摂取量に刺激を入れるためのインターバルトレーニングは「酸素摂取量が高い状態(=走る速さが速い状態)でできるだけ長い時間維持すること」が重要でした。
一方で、ショートインターバルでは短い時間で疾走が終了するため、疾走している間のエネルギー供給割合として、解糖系から発生するエネルギーを使う割合が大きいことが考えられます。
したがって、ショートインターバルでは、解糖系への刺激が比較的強くなることが予想されます。
3000m以上の種目に対する特異性の面ではロングインターバルが有利
目標にしているレースの距離が3000m以上である場合には、ショートインターバルが競技結果に直接結びつきにくいと考えられます。
理由としては、短い疾走距離でレストを挟んでしまうため、走り続けなければならない「特異性」が劣るからです。
一方、1500m以下の種目に対しては、ショートインターバルのほうが特異性が高くなる可能性はあります。
疾走距離が近くなるという点に加え、ショートインターバルでは、解糖系への刺激が強くなるため、解糖系から発生したエネルギーを多く使う、1500m以下の種目に対しては、特異性が高くなる、と言えそうです。
以上の通り、ショートインターバルとロングインターバルにはそれぞれ特徴があるため、目標とするレースに向けてトレーニングを使い分けてみましょう。
トレーニングをするうえで、その他メリット
ショートインターバルには、上記で述べていない下記メリットがあると考えています。
- 練習場所を確保しやすい
- 単独でもやり切りやすく、継続的に行うことができる
市民ランナーにとって、インターバルトレーニングを行う練習場所の確保は意外と難しいです。
陸上競技場が空いている時間にトレーニングすることがそもそも難しかったり、ロードで行う場合には、信号が無く車の通りが少ないフラットな平地を確保する必要があります。
ショートインターバルですと、確保すべき場所が400m程度であるため、練習場所は見つけやすい、ということができます。
また、ロングインターバルと比較して疾走時間が短いため、練習中に感じる苦しさが短くなります。
単独で練習していると、練習がきつくて途中で諦めてしまうことがあり、結果としてインターバルトレーニングの効果が半分以下になってしまう、といったことも考えられます。
ショートインターバルでは練習をやり切りやすく、練習の継続性が確保できると考えています。
ショートインターバルを取り入れる時期
ショートインターバルは、その目的によって取り入れる時期が異なります。
乳酸性作業閾値改善が目的の大ボリュームなショートインターバルであれば、レースシーズンから離れたオフシーズンなどに取り入れることが多いです。
一方で、3000mレースペースへの調整練習という位置づけであれば、レースに近い時期に取り入れるべきです。
ショートインターバルに求める目的で、取り入れる時期を決めましょう。
ショートインターバルの具体的練習例
- 距離:200~600m/1本あたり
- 設定ペース:90~100%VO2max(=10000m~3000mレースペース)
- レスト:疾走時間の50~90%
設定ペースとレストの決め方によって、ショートインターバルで得られる効果は大きく違ってきます。400mのショートインターバルを例に考察します。
練習メニューに正解はありません。自分自身が狙っている目的に合わせて疾走ペースとレストを設定します。
疾走ペース
90~100%VO2max程度に設定します。
わかりやすく言い換えると、3000mレースペース(=100%VO2max)から10000mレースペース(90%VO2max)です。
理由としては、ショートインターバルの大きなメリットである速筋繊維への刺激を高めるためです。
設定ペースを具体的に決める方法は次の記事を参考にしてください。
レスト
レストは「ジョギングで繋ぐ」か「その場で休憩する」の2パターンがあります。
レストをジョギングで繋いだ場合は疾走間を30~40秒程度でジョギングすることになります。ほとんど心拍数が落ちない状態で次の疾走となります。
疾走速度を上げ切ることは難しいですが、最大酸素摂取量への刺激は大きくなることが予想されます。また、レースに近い状況でトレーニングを行うことになりますので特異性は向上しそうです。
レストが短い分、レースに近いトレーニングと言えます。
二つ目としては、レストをその場で休むパターンです。これは、TwoLapsの新谷仁美選手のトレーニングで紹介されていました。
新谷選手は「走りのフォームが崩れず集中することができる」とコメントしております。私自身が行った際も同様に感じました。
その場でレストするため、心拍数は疾走前にある程度低下します。その結果、疾走速度を上げることができる傾向があります。
レストをジョギングするよりも、より高い運動強度で疾走できるため、速筋繊維への刺激は大きくなります。ただし、その場休憩を行う場合はレースの状況とは大きく異なることになるため、特異性は低下すると考えられます。
らんしゅー自身の実践例
私自身が取り入れているショートインターバルのメニュー例を示します。
- 400m × 25 r30s(10000mレースペース)
- 400m × 15 r30~45s(5000mレースペース)
- 400m × 10 r60s(3000mレースペース)
ショートインターバルは、狙っている目的によってペースと繰り返し本数などを調整しています。
乳酸性作業閾値の改善が目的であれば、ペースは10000mレースペース程度に抑えボリュームを増やします。
3000mレースに備えた調整練習であれば、3000mレースペースまで疾走速度を上げてレストを少し長めにとる、などの調整をします。
ショートインターバル効果・メリットのまとめ
ショートインターバル特筆すべき効果・メリットをまとめます
- ロングインターバルと比較して疾走速度を上げることができるため速筋繊維への刺激が入る
- 速筋繊維への刺激が入ることで、乳酸代謝能力の内、血中への乳酸拡散能力向上が見込める
- 練習場所の確保がしやすく、単独でもやり切りやすいため継続性がある
- 疾走ペースとレストの設定方法によってえられる効果が異なる
フルマラソンに向けたトレーニングとしてはショートインターバルよりも、ロングインターバルのほうが適しているといえそうです。
しかし、5000m等短めのレースに対しては、ショートインターバルによる速筋への刺激が有効に働く可能性がありそう、ということが分かります。
今後の練習に反映させてみてください。
参考文献:








コメント