※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。
【マラソンペース(Mペース)でのトレーニング効果と練習法】生理学とトレーニング原則から考察
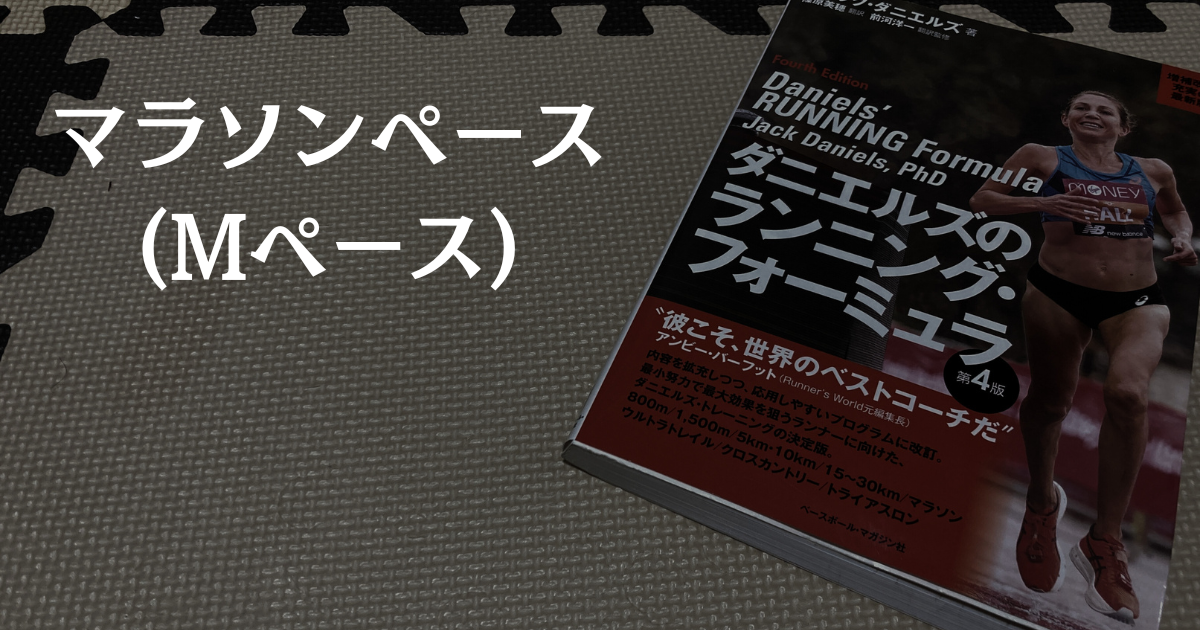
- Mペースってなに?
- マラソンのレースペースで走ることで得られる効果は?
- マラソンペースでのトレーニングの適切な実施方法が知りたい
フルマラソンで記録向上を目指している方でマラソンレースペースでのトレーニングをする方も多いと思いますが、得られる具体的な効果まで理解できている方は少ないのではないでしょうか。
フルマラソンで記録を狙うためのトレーニングとして、実際のフルマラソンレースペース(以下Mペース)でトレーニングを行うことが効果的ではない場面も多くあるのが事実です。
私は社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程を走り競技志向でランニングに取り組んでいます。
今回はMペースでのトレーニング効果と適切な練習法について考察・解説していきます。
実際、ダニエルズのランニング・フォーミュラやリディアードのランニングトレーニングの両理論でも、フルマラソン用のトレーニングとして、必ずMペースが組み込まれています。
マラソンの記録向上に必要不可欠なトレーニングではありますが、適切な実施方法やタイミングがります。
本記事を読めば、Mペースでのトレーニングで得られる効果を理解することができ、適切なペースを設定し、トレーニングを効果的なタイミングで実施できるようになります。
- ダニエルズのランニング・フォーミュラでは「Mペース」と呼ばれる
- マラソンペースはスイートスポットに該当し、少ない疲労で高い効果を得られるトレーニング
- フルマラソンに対して「特異性」が伸びる
- ダニエルズ理論では週1回程度の頻度でMランニングが組み込まれている
マラソンペース(Mペース)の設定ペース、走行距離の設定
ダニエルズのランニング・フォーミュラで紹介されている、Mペースのトレーニング設定ペースと練習方法を紹介します。
設定ペース
Mペースでのトレーニングは、フルマラソンでのレースペースで行います。直近でフルマラソンに出場し記録が分かる方は、その記録を元にペースを決めることができます。
一方、フルマラソンへの出場が無い方、もしくは前回出場してから長い時間が経過している方は、ハーフマラソンや5000mの記録からVDOT Calculatorで計算することになります。
「Marathon」行に示されているのがMペースとなります。

走行距離
ダニエルズのランニング・フォーミュラでは、1回のトレーニングで行うMペースでの走行距離上限は週間走行距離の20%以下が推奨です(怪我防止の観点から)。
例えば1週間で100km走っている方であれば、1回のトレーニングで行うMペースは20km以内に抑えましょう、ということになります。
Mペースでのトレーニングに期待できる効果(筆者体験踏まえて)
Mペースでのトレーニングに期待できる効果は以下の通りです。
- LT値向上
- フルマラソンに向けた特異性の向上
ダニエルズ理論での説明
Mペースでのトレーニング効果について、ダニエルズのランニング・フォーミュラには以下の記載があります。
Mペースランニングをする目的は、実際のレースペースになれること、そしてそのペースで給水をとる練習をすることである。したがって、Mランニングの主な効果は、メンタル的なもの、つまり設定したペースで走る自身を高めるものと言ってもいい。生理学的な効果はEランニングとまったく変わらない。
ダニエルズのランニング・フォーミュラ第3版
ダニエルズ理論によれば、マラソンペースでのトレーニングはEペースで行うジョギングと生理学的な効果が変わらないと述べられています。
Easyペースでのジョギングで得られる効果は次の記事でまとめています。
しかし、私が自分自身でマラソンペースのトレーニングを取り入れた時、「本当にジョギングと同じ効果しかないのだろうか」と疑問を持ちました。
Mペースでトレーニングを行っていると、徐々にLT走と同じきつさを脚に感じたことがきっかけです。
自分の中で、「Mペースでもやり方によってはLT走と同じ効果を得ることができるのではないか」と考えていました。
MペースランニングでのLT値向上
結論として、MペースでのランニングトレーニングではLT値の改善効果を得ることができます。
運動強度を5段階に分けた場合、Mペースはzone3に該当します。
| 運動強度 | 強度名称 | 強度区分 | ※1 %HRmax | ※2 %VO2max | ※3 血中乳酸濃度 mmol/L |
|---|---|---|---|---|---|
| zone1 | Easy | 低強度 | 60~71 | 50~65 | 0.8~1.5 |
| zone2 | Moderate | 低~中強度 | 72~82 | 66~80 | 1.5~2.5 |
| zone3 | LT | 中強度 | 83~87 | 81~87 | 2.4~4.0 |
| zone4 | OBLA | 高強度 | 88~92 | 88~93 | 4.1~6.0 |
| zone5 | VO2max | 高強度 | 93~100 | 94~100 | >6.1 |
| Sprint | 高強度 | - | 100~ | - |
- ※1 %HRmax:最大心拍数に対する割合。
- ※2 %VO2max:最大酸素摂取量に対する割合。
- ※3 血中乳酸濃度:血液中の乳酸濃度。専用の測定機器でしか測ることができない。競技レベルが向上すると、同じ強度でも血中乳酸濃度の数値は低下する傾向がある。
zone3の強度で行うトレーニングは別名「スイートスポットトレーニング(SST)」と呼ばれます。SSTは最小限の疲労で最大限の効果を得ることができるといわれており、非常に効率が良いトレーニングです。
SSTを積み上げていくことで、LT値を継続的に改善することが可能です。
フルマラソンレースに向けた「特異性」の伸長
Mペースでのランニングを繰り返すことで、Mペースに対するランニングエコノミー(マラソンペースを楽に走れるようになる)が向上します。これを「特異性の向上」と呼びます。
マラソン界で有名なコーチとして知られているレナート・カノーヴァという方がいらっしゃいます。
ウィルソン・キプサング選手(元世界記録保持者)やソンドレ・モーエン選手(元ヨーロッパ記録保持者、2017福岡国際優勝)等の有名選手指導していました。
そのカノーヴァコーチが重要視している思想としてトレーニングの特異性が挙げられます。
カノーバシステムによると、「マラソンペース90%以上の練習以外はすべて特異的ではない」と考えているようです。
極端な例を挙げると、カノーヴァコーチのトレーニングではMペースの98%に近いペースで40kmを行うことがあるそうです。
「特異性」はトレーニングの5大原則でもよく知られていることです。カノーバシステムを採用した選手が実績を残していることからも、「特異性」の重要性はマラソンにも当てはまるようですね。
NTT西日本の竹ノ内佳樹選手、2020年福岡国際マラソンで優勝したGMOアスリーツの吉田選手も、他種目に対してフルマラソンのVDOTが飛び抜けて高いです。
このことからも、種目に沿ったトレーニングを特異的に実施することが、記録を向上させるうえで重要であることが示されています。
Mペーストレーニングのメニュー具体例
Mペースでのトレーニング例を紹介していきます。
ペース設定方法(レースまでの時期による設定方法)
ダニエルズのランニングフォーミュラでは、フルマラソンレース18週間前からのトレーニングメニュー例が記載されています。
その中で、トレーニングでの設定ペースを決める際には、次のように推奨されています。
M、T、I、Rの各トレーニングのペースをVDOTから求める場合には、現実的に考えるべきである。そして、VDOTは10km以上のレース結果を元に決める。基準とするレースは、距離が長いほど、そして最近のものであるほど良い。・・・。最初の6週間のVDOTを決めるには、直近のレース結果に相当するVDOTと、マラソンで予想されるVDOTより2ポイント下のVDOTとを比べ、低い方を採用する。次の6週間は、VDOTを1ポイント上げ、最終の6週間ではもう1ポイント上げてトレーニングを行う
ダニエルズのランニング・フォーミュラ 第3版
フルマラソンにおける準備期間においては、多少VDOTのレベルを下げてトレーニングを開始します。
具体的トレーニング例
ダニエルズのランニングフォーミュラに記載されている、具体的トレーニング例を紹介します。
※E:Eペース、M:Mペース、T:Tペース。EとはEasyペースの事であり、ジョギングのペース。TとはThresholdの略でありLTペースの事。
- E(15分~60分)+M(30~80分)+E(10~15分)
- E(15分)+M(5~50分)+T(5分)+M(5~50分)+T(5分)+E(10分)
オーソドックスなMペースでのペース走や、Tペースを挟んだ変化走等があります。
Mペースでランニングする前後でEペースでのジョギングを行うことで、ウォーミングアップとクーリングダウンを兼ねています。
Mペース前に行うEペースでのジョギングを60分まで延ばすことで、ロングランの要素を織り交ぜることも可能です。
Mペースのトレーニングを取り入れるべき時期
Mペースでのトレーニングは目標としているフルマラソンレースの2か月くらい前から取り入れ始めるのが理想的です。
Mペースでのトレーニングの主目的は、レースに対する特異性の向上です。レースから遠い時期には、低強度のジョギングや高強度のインターバル走などで身体の機能を高めておくことが必要です。
皆様の参考になれば幸いです。
参考文献:








コメント