※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。
【距離走(ロングジョグ)】の効果を最大化する方法を考察 適正ペースや距離は?
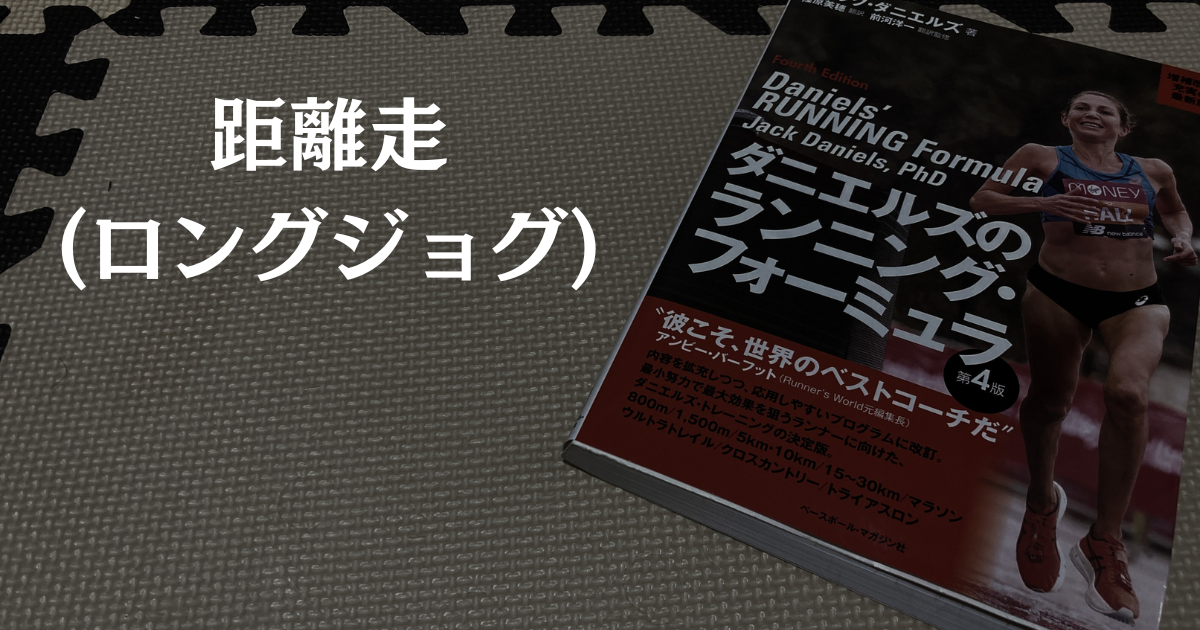
- 距離走(ロング走)はどんな効果があるの?
- 距離走を実施すべきタイミングは?
- 距離走のやり方が分からない
距離走を取り入れたいけど、ペース設定やどのくらいの距離を走ればよいのかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
私は社会人からランニングを始めた市民ランナーです。月500km程走り、競技志向でランニングに取り組んでいます。
ここでは、距離走(ロングラン=ロングジョグ)トレーニングの効果を最大化するための方法を考察していきます。
また、運動生理学の観点から距離走で得られる効果についても考えていきます。
マラソン界において二大理論といっても過言ではない、ダニエルズのランニングフォーミュラとリディアードのランニングトレーニングでも週に一回以上の距離走が推奨されています。
本記事を読めば、距離走において、走るべき距離・適正ペース・実施するタイミングについて理解することができます。
はじめに結論を述べます。
- 距離走は脂質をエネルギー源として使う能力の向上が目的
- 設定ペースはEasyペース~Moderateペースが適切
- フルマラソンレースを想定した距離走であれば、マラソンペース近くまで上げて特異性を高める
- 距離走で行う距離は、週間走行距離の25%以下を目安にする
距離走とは?距離走の呼び名について
ダニエルズのランニングフォーミュラでは「Lランニング」、リディアードのランニングトレーニングでは「有酸素ロングラン」と呼ばれるトレーニングです。
「ロングジョグ」といわれることもあります。
指導者や参考書によっては、ペースによって呼び名を使い分けている例もあります。
例えばジョギング程度のペースで長い距離を走る場合はロングジョグ、ある程度速いペースで走る場合はロングランなどと使い分けます。
指導者として正しく言葉を定義する必要があれば、明確に言葉を使い分ける必要があります。本記事では、正確に情報を伝えるため下記の定義とさせて頂きます。
- 距離走:ロングジョグ、ロングランの総称
- ロングジョグ:Easyペースの中でも遅い方(もしくはEasyペースよりも遅め)での距離走
- ロングラン(ロング走):Easyペース~マラソンペース、比較的速いペースでの距離走
※Easyペースとは、ダニエルズのランニングフォーミュラで使用される名称です。
距離走は「長い距離を一度で走るトレーニングの総称」とします。
距離走で得られる効果
距離走の効果を考えるためには適正な設定ペースを検討することが必要です。目的が理解できていれば、適正なペースも自然と理解することができます。
Easyペースの距離走で得られる運動生理学的効果
距離走で得られる生理学的効果は、距離走を行うペース設定によって変わってきます。
距離走をEasyペースで行う場合は、距離走で得られる効果はジョギングと同様です。
具体的には、怪我への耐性・心筋の発達・毛細血管新生・活動筋の適応・ミトコンドリアの新生/機能向上を期待することができます。
次の記事ではEasyペースのトレーニングで得られる効果についてまとめています。
距離走特有の効果を得るためには?
ジョギングと同じ効果しか得られないのであればあえて長い距離を一度に走る必要はありません。
距離走でしか得られない効果もあるから、エリートランナーにも広く取り入れられていると考えます。
あえて距離走を行うことで得たい効果としては「フルマラソンレースに対する特異性」であると考えています。
フルマラソンに対する特異性とは「筋肉のグリコーゲンが減少した状態でも体を動かし続けることに慣れること」と言い換えることができると考えています。
フルマラソンでは「30kmの壁」が知られています。「30kmの壁」とは筋グリコーゲンが減少し、筋収縮がスムーズにできなくなる状態のことを指します。
つまり、筋グリコーゲンが少なくなって足が動かなくなることを可能な限り発生させないようにすることが一つのポイントになるわけです。
距離走で得られる、フルマラソンレースに対する特異性は、主に以下の通りだと考えています。
- 筋グリコーゲンが減った状態で体を動かし続けることに慣れる
- ランニングエコノミーの向上により少ないエネルギーで走れるようになる
- 距離走を含めた持久性トレーニングの積み上げで、筋繊維のミトコンドリア数および機能が向上し、脂質の代謝能力が向上する
マラソンでは筋グリコーゲンが少なくなって足が動かなくなってしまうぎりぎりで走り切ることが重要です。距離走を重ねて行うことで、「これくらいなら走り続けても大丈夫だ」と体に覚えこませることが必要です。
長い時間運動を継続していると血糖値が低下していきます。ある一定以上に血糖値が低下すると、筋繊維への糖質供給が制限されるようになります。そうなると一気にハンガーノック状態となり、足が動かなくなる状態となります。
ある意味「リミッター」のような機能が人間には備わっていますが、距離走を重ねることで、グリコーゲンの減少に「慣れ」、リミッターの上限を上げることができるようになると考えられます。
また、距離走のように長い時間走り続けることで自然と楽なフォームが身に付きランニングエコノミーが向上します。同じスピードでもエネルギー消費量は少なくて済むようになり、結果的に筋グリコーゲンが減りにくくなります。
距離走に限りませんが、継続的な持久性トレーニングによってミトコンドリアの数や機能が増加し、脂肪を使う機能が徐々に高まっていきます。
距離走の設定ペース
以下では距離走での設定ペースについて解説します。
距離走の設定ペースは基本Eペース
これまで述べてきた通り、脂肪の代謝能力を向上させることが主目的の場合、距離走での走行ペースは「ジョギングと同じペース=Eペース」が推奨です。
VDOT Calculatorを使ったEペースの求め方については次の記事を参考にしてください。
その他の点で重要なことは「怪我無く、練習を継続し、練習の目的を達成すること」です。
ダニエルズ理論では、基本的に「マラソンペース」と「Eペース」の生理学的効果は同じ(効果の大小はある)と紹介されています。
毎回距離走においてマラソンペースで走っていては、負担が大きく怪我も多くなり、長い期間でみると練習を継続できない可能性が高いです。
練習の継続性と距離走の目的を理解できていれば、ジョギングペースでも脂質の使用能力向上効果が得られることがわかります。
距離走のペースを上げる場合の意図
フルマラソンレースに近づいてきたときは、距離走のペースを徐々にレースペースに近づけていくことが必要です。
距離走で特に得たい効果として「フルマラソンレースに対する特異性」を述べました。
特異性は、できるだけレースペースに近いほうが、より効果を高めることが可能です。
したがって、持続可能な範囲で、距離走のペースは目標とするフルマラソンレースに近づけていくことが必要です。
実業団選手(例:吉田祐也選手)の距離走
実際にエリートランナーのトレーニングを見てみます。
例えば、GMOアスリーツの吉田祐也選手の例です。2020年福岡国際マラソンで優勝した実力者です。
彼は練習をnoteで公開していますが、ロングジョグを非常に重要視していて、その走行ペースは3:45~4:00/kmだそうです。
フルマラソンを3:00/kmで走ってしまう選手としてはとてもゆったりしたペースです。Easyペースの中でも最も遅い領域、もしくはEasyペースよりも遅めの設定です。
吉田選手は、ロングジョグ一回当たり120~150分(夏場は90~120分)で行っていたそうです。
距離走の適正な距離は週間走行距離の25~30%以下
これまで、距離走は運動継続時間が長ければ長いほど脂肪の利用割合が増加すると述べてきましたが、一度で走る距離が多いとケガをします。
怪我予防の観点から、上限距離を決めておく
ダニエルズのランニングフォーミュラでは、一回での走行距離に上限をかけることが推奨されています。
- 1週間当たりの走行距離が64km未満の方は、週間走行距離の30%以内
- 1週間当たりの走行距離が65km以上の方は、週間走行距離の25%以内、もしくは150分以下のどちらか短い方
上限が設けられているのは、怪我防止のためです。
実業団の選手が30kmを4分/kmのペースで走れば120分で終わりますが、5分/kmの市民ランナーが同様に30kmを走ると150分かかります。
実業団の方にとっても市民ランナーにとっても、ランニングのペース的には体にかかる負担が同じEペースであっても、市民ランナーのほうが走らなければならない時間が長く、負担が大きいです。
市民ランナーの方が5分/kmのスピードで24kmしか走れなかったとしても、走行時間は120分となるため、十分長いと言えます。
ただし例外として、初心者がマラソン大会で完走を目指している場合やウルトラマラソンに向けたトレーニング等、どうしても練習で長い時間走っておかなければならない時もあるかと思います。
そのような場合には、自分の体と相談しつつ、怪我をしないトレーニング量を模索しながら、慎重にトレーニングを進めましょう。
そのような場合を除いては、怪我防止のため走行距離に上限を設けながら練習を継続するべきです。
距離走で走る1回当たりの距離を伸ばす方法
体にかかる負担を抑えて怪我を防止しながら、一回で走る距離を伸ばしていくには、普段から走っている距離を徐々に伸ばしていくことがまず優先です。
ダニエルズ理論では、走行距離を伸ばす方法として、一回の練習あたり+1.6kmにとどめ、少なくとも4週間(=つまり1か月)は同距離を維持すべきことが推奨されています。
具体例で説明します。
1日当たり10km・月間300km程度走っていたランナーが走行距離を伸ばす場合、まずは1回当たり11.6km程度(=月間で348km)とし、少なくとも1か月間は維持するということになります。
実際には、毎日同じ距離を走るわけではないと思うので、最大距離(週間走行距離の25~30%以下)を意識して、1回の練習あたり1.6kmずつ伸ばす、といったことになると思います。
走行距離の伸ばし方は、管理人が実際に怪我を経験してきたうえでとても重要だと思うポイントです。
これまで、脚を故障してきた過去を振り返ると、いずれも走行距離を伸ばしたタイミングです。特に膝を痛めてしまった時は、約2~3か月間、棒に振ってしまった結果となりました。
怪我無く継続的にトレーニングへ取り組むためにも、走行距離を伸ばすときには十分に注意しながら行っていきましょう。
フルマラソンに近い距離を練習で走ってはいけない?
フルマラソンレースに向けて、レースに近い距離を走りたいランナーもいると思います。結論としては、トレーニングでもレースに近い距離を走っても良いと考えています。
ただし、毎週行うには怪我のリスクが高まります。したがって、月1回や3週間に1回など、頻度を下げて行えば怪我のリスクも低下すると考えられます。
与が高いことが予想されます。
実施するタイミング:ポイント練習翌日に行うと効果増大
距離走を実施する適切なタイミングを考察します。
パターンとしては、ポイント練習の一つとして組み込むか、セット練習(バックトゥバック)2日目のトレーニングとして組み込むかのどちらかです。
マラソンペースに近いペースまでペースアップする場合は、ポイント練習の一つとして取り組むことになります。
一方、サブのトレーニングとして組み込んでいる場合、距離走の目的(有酸素能力の発達)を考えると、セット練習2日目のトレーニングとして組み込んだ方が効果が高いと考えられます。
理由としては、1日目のポイント練習で筋グリコーゲンが減少した状態で距離走を行うことで、脂質代謝機能がより適応すると考えられるためです。
しかし、距離走にはじめて取り組む市民ランナーの方には、パターン一つ目である、ポイント練習の一つとして組み込むことをおすすめします。
※ポイント練習とは、「ジョギング」とは分けて考える「負荷の高いトレーニング」のこと
理由としては、まだ長い距離・時間を走ることに慣れていない状態で、急に負荷を上げてしまうことで、怪我のリスクが高くなるからです。
経験を積み、距離走にもある程度慣れてきたらポイント練習の翌日に距離走を行う、セット練習に取り組んでみましょう。
距離走では、筋グリコーゲンが減少した状態でランニングを継続することで、練習効果(脂肪の代謝能力向上)が増大します。
前日に負荷が高いトレーニングを行うと、筋グリコーゲンが消費された状態となります。
翌日になっても糖分は回復しきらないため、距離走を行う前から、筋グリコーゲンが消費された状態となっているため、走り始めから普段よりも脂肪の利用割合が高くなるなります。
つまり、同じ2時間走る練習でも、脂肪を使う量には「差ができる」わけです。
以上の理由から、慣れないうちはポイント練習の一環として行うことをおすすめしますが、慣れてきたら是非、ポイント練習の翌日に行うセット練習として距離走に取り組んでみましょう。
- 距離走に慣れないうちはポイント練習の一環として取り組もう
- 慣れてきたらセット練習2日目の練習メニューとして組み込んでみよう
- 体の糖分(=筋グリコーゲン)が少ない状態で運動を継続することが重要!
これまで、なんとなく距離走を行ってきていた方も、距離走の意味や目的をしっかり理解することができれば、適正ペースや実施するタイミングも見直すことができます。
フルマラソンの記録更新に向けて、効果の高い距離走を行っていきましょう。
参考文献:









コメント