※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。
2022/06/10【3000mレース振り返り】今後の方針と目標-rev.8
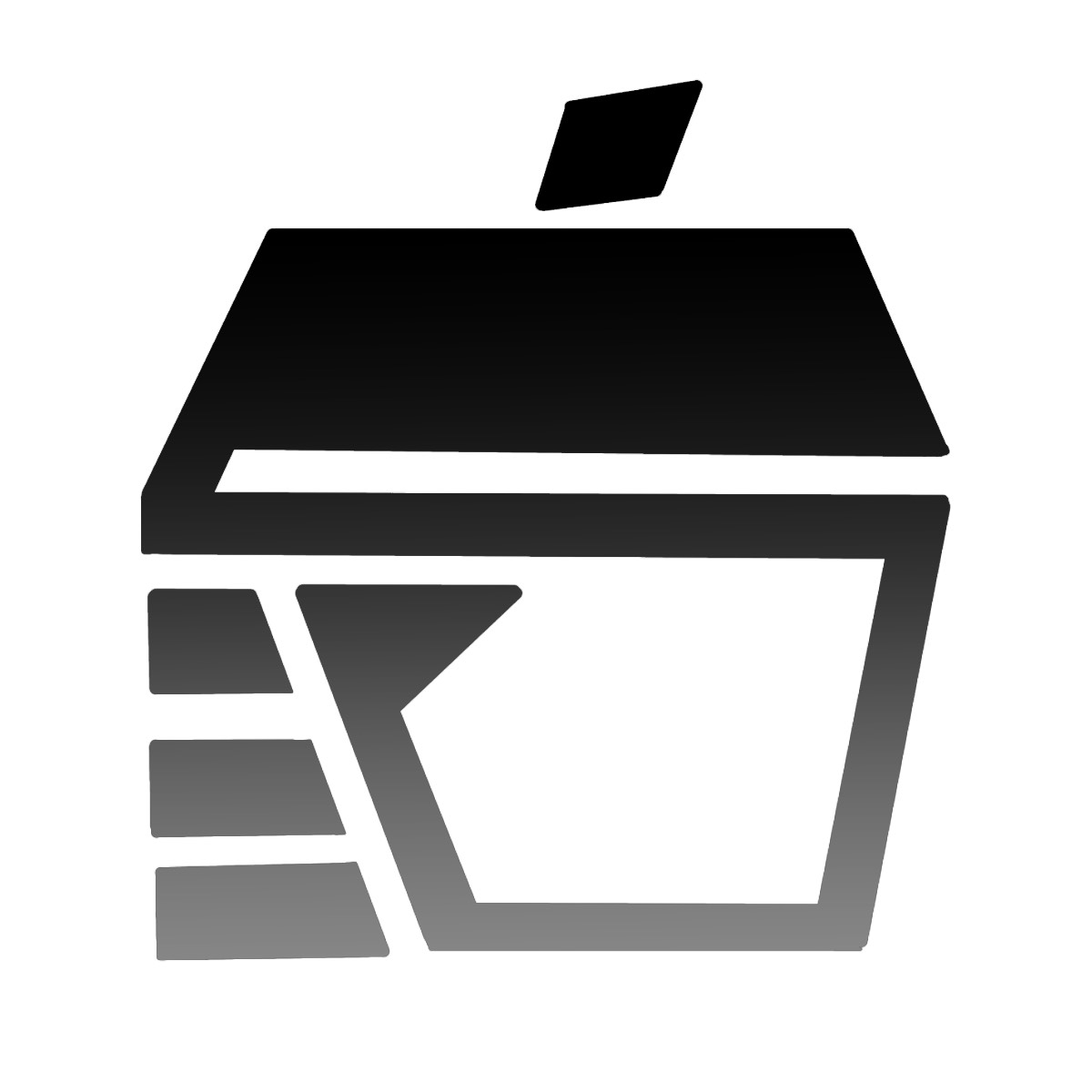
こんにちは。らんしゅーです。
別の記事で自己紹介をしていますが、大学まで長距離種目の経験が無い市民ランナーです(スポーツの経験は豊富です)。
2022年も前半が終わろうとしています。昨日3000mレースが終わったところで、一旦振り返りを行おうと思いました。というのも、2021年秋頃と現在を比較してほとんど記録が向上していない可能性があるためです。
始めに記載しておきますが、記録が伸びていないからと言って方針転換をすることは考えていません。トレーニングの方向性は正しいと考えています。
本記事では、3000mレースの振り返りから始め、なぜ昨シーズンから記録が伸びてこないかを検討します。
3000mレースの振り返り
レースレポートでも記載している通り、今回の3000mレースは4月の5000mで挙がった課題の進捗を測る位置づけでした。その課題は下記となります。
- 陸上競技場、スパイクを使用したトレーニング不足
- ランニングピッチを高めた時の走行感覚が無い
- 解糖系トレーニング不足
- 身体機能的にピッチを上げることができない
単調直入に言うと、4月に挙がった課題に対しては、全てにおいてある一定の成果が得られました。3000mレースでは1000mの入りが3:02/kmであったにもかかわらずある程度余裕を持って通過できたこと、ランニングピッチも有意に向上させることができていることが分かっています。
しかし記録としては、9分24秒(VDOT63.1)でした。2021年10月の5000mでは16分14秒(VDOT63.5)であり、距離が違うため単純比較はできませんが、ほとんど記録の伸びが無いと言える結果だと考えています。
走った状況が異なるだろ、という意見も出てきそうですが、これは偶然なのですが、上記2レースは気温・レース会場・レース開始時刻等、ほとんどの条件が揃っていたのです。
これは、現状の実力であり、記録が伸びていないことを事実として受け入れる必要がある事を意味しています。
昨シーズンから記録が伸びていない理由の考察
3000mの記録で比較すると、2021年6月;9分34秒、2022年6月;9分24秒。およそ10秒のタイムアップです。記録は伸びているのですが、練習量から考えると「もっと伸びていてもおかしくない」感触です。
「伸びていない」というよりも「伸び率が悪い」という方が正確かもしれません。
5000m及びハーフマラソンの記録推移を示します。
| 年度 | 5000m | ハーフ |
|---|---|---|
| 2019 | 17分30秒(58.2) | 1時間17分20秒(60.7) |
| 2020 | 16分21秒(63.0) | 1時間15分40秒(62.3) |
| 2021 | 16分14秒(63.5) | 1時間12分29秒(65.4) |
| 2022 | 16分26秒(62.8) | ー |
特に「(トラックで行われる)5000m以下の種目について記録が伸びていない」ということも言えそうです。
従って、問題としては「①記録の伸び率が悪い・②トラックでの記録が伸びない」の2点となる事が分かります。
ここでようやく主題に入ります。記録の伸び率が低下している要因は下記を考えています。
- 5000m以下の種目に向けたトレーニングの特異性が不足している
- 普段のトレーニング負荷が高く、リカバリーが足りていない
5000m以下の距離は基本的にトラックでレースが行われます。また、距離が短くなってくるにつれて、生理学的には「解糖系」及び「最大酸素摂取量」の寄与具合が高まってきます。
この点を克服するため、4月の5000m後から約2か月間、トラックでのトレーニングと解糖系の強化を行い、レース前に向けて最大酸素摂取量の改善に取り組んできました。特に最大酸素摂取量は取り組み始めて割と短い時間で効果が出ることが分かっています。
しかし結果として、4月の5000mで記録したVDOTと6月の3000mで記録したVDOTはほぼ同一であり、特異性を高めることによる効果は小さかったことが分かります。
ただこの点については後述しますが、レースに向けて特異的なトレーニングを進めた傍ら、トレーニングボリュームはほぼ維持、もしくはわずかに増やしてしまった、という問題がありました。
本来、トレーニングの特異性を高めることで「トレーニング一回当たりのスピード値=負荷」は高まるため、トレーニング全体の負荷は落とす方向で調整していく必要があります。しかし、今回は負荷はほぼ維持しながら、質だけ上げようとしてしまっています。
その結果、高負荷トレーニングに対して体の適応がうまく進まず、効果が出にくかった可能性があります。
従って、現時点で記録の伸び率が低下している要因として最も可能性が高いのは、「普段のトレーニング負荷が高く、リカバリーし切れていない」点だと考えています。
記録が継続的に低下していることなく、睡眠障害や心拍数増加等の現象もみられていないので、オーバートレーニングとまでは行きませんが、少し「オーバーリーチ気味」である可能性を疑っています。
現在は下記のサイクルでトレーニングを進めています。
| 曜日 | トレーニング |
|---|---|
| 月曜 | Easy or OFF |
| 火曜 | AM : Speed Training(1500~3000m RP) PM : Easy |
| 水曜 | Easy |
| 木曜 | AM : LT Interval(2000m*5) PM : Easy |
| 金曜 | Easy |
| 土曜 | LT Interval(1000m*10) |
| 日曜 | Long Jog(Easy) |
週3回のポイント練習を組んでいます。本来、LT Intervalの強度を正しくコントロールすることで、体が疲労しすぎることを防ぐ必要がありますが、このLT Intervalの強度が高すぎることで、週を通して疲労から回復しきれていない可能性があると考えています。
この考えに至った背景には、インゲブリクトセン兄弟のトレーニングメソッドの背景にあるマリウスバッケンの理論があります。そこではLT Intervalの強度を精密にコントロールしないとオーバートレーニングとなる傾向にある、とされていました。
自分のトレーニングを振り返ってみると、LTトレーニングとしては少し負荷が高すぎる強度で行っていたと感じました。
トレーニング強度を下げ、リカバリー優先にしてみる
以上の考察から、トラックでの記録向上を狙って、通常トレーニングの負荷を下げ、リカバリーを優先させることを実行しようと考えています。
具体的には、下記のアクションを行います。
- LT Intervalの強度を意図的に下げる
- ポイント練習前後に行っていたジョグを短くする
- 2週(総負荷高)-1週(総負荷80%)のサイクルとする
LT Intervalの強度が高すぎることで、リカバリーしきれていないことが考えられます。強度を心拍数やペース設定で管理することは難しいため、主観的強度での評価を主に用い、今よりももう少し余裕を持ってLTトレーニングを行うようにします。
本来であれば、血中乳酸濃度等を測定できる環境にあればベストなのですが、それはさすがに難しいので、心拍数・ペース設定・主観的強度を組み合わせて、適切なトレーニング強度へと調整していこうと考えています。
また、これまでは低強度トレーニングとしてのジョグを、ポイント練習前後で割と長めにとっていました。メリットも多くありますが、現時点で達成したい目標として、1500m~10000mでの記録向上に対しては、費用対効果(=疲労に対しての効果)は悪いと考えます。
従って、ジョグの距離を少し短くし、または、二部練等分割して行うようにします。
そして、最も大きく変更する点が、意図的に「負荷を下げる週」を入れることです。これまでは、毎週100%の負荷でトレーニングを継続してきましたが、やはり、集中的に回復する週も必要であると判断しました。
この考えのもとになっているのは、前項でも述べたマリウスバッケンの理論です。マリウスが提案するトレーニングサイクルとして提唱されているのが、2週-1週サイクルでのトレーニングであり、3週間のうち1週間は、他2週間と比較して負荷を下げる方がベターである、と言っています。
以上3点の変化を与えようと考えています。どれについてもトレーニング負荷は下がる方向です。
次の記録評価方針
次のレース予定は、6/18に中京大土曜競技会5000mを考えています。4月から継続的に取り組んできた解糖系強化とVO2maxの改善が着実に進んできており、パフォーマンスが向上してきたことを感じています。
気温の高さから、当初計画では1500mに出場する予定でしたが、梅雨に入り、そこまで高温にならなさそうだということ、パフォーマンスが上がってきたところでとりあえず16分切りをしておきたいこと、の2点から、5000mへと変更しました。
5000mが終わったところで、課題を抽出し直し、その後のトレーニング計画へと反映させたいと考えています。






コメント